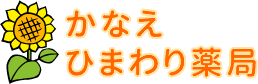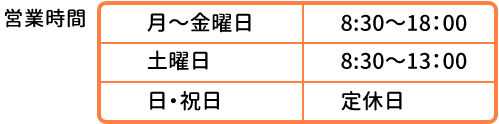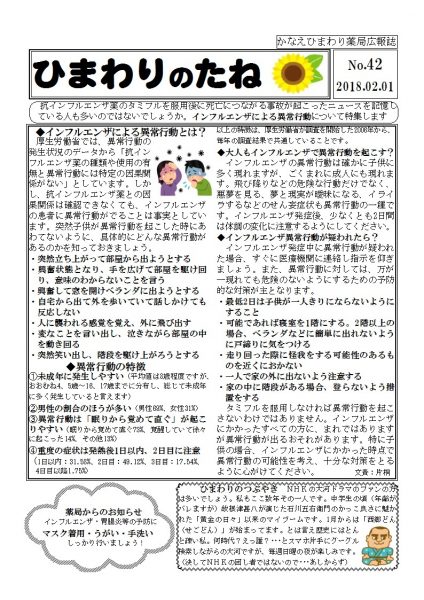かなえひまわり薬局日記
第23回飯伊病診部会学術研修会並びに特別講演会
投稿日: カテゴリー:かなえひまわり薬局日記, 学習会 from:sio
2月24日(土)にシルクホテルで開催された第23回飯伊病診部会学術研修会並びに特別講演会に出席しました。
学術研修会では6つの演題発表がありました。活動報告や調査報告、症例報告などを通して病院での薬剤師の活動を知ることができ、とても興味深かったです。
特別講演会は、いちはし内科医院の市橋浩司先生をお招きして、「咳と喘息とCOPDと~吸入療法をふまえて~」というテーマでご講演頂きました。
咳の基礎から、喘息・COPDについて詳しく説明して頂き、各吸入薬の特徴や到達部位の違い、デバイスの種類、高齢者への吸入指導の工夫など紹介してくださいました。吸入指導は、初回だけでなく、一定期間経過した時点での再指導も重要だそうです。
今はたくさんの種類の吸入薬があるため、吸入回数や吸入器の見易さ・使い易さなどから、個々人に合った吸入薬を選択することが可能です。吸入がきちんと行えているか評価し、病院と薬局が情報共有していくことの大切さを学びました。
学生さんアルバイト
投稿日: カテゴリー:かなえひまわり薬局日記 from:ryoko
2月に入ってから雪が降る回数も多くまだまだ冬真っ只中という感じですが、大学生の皆さんの中には春休みに入っている学生さんもいて、今年度奨学生になった1年生の学生さんがアルバイトに来てくれました★高学年の学生さんは実習の準備や研究室などでかなり忙しい毎日を送っているようです。
今回のアルバイトは2日間でしたが、すぐに仕事を覚え一生懸命ヒート出しをしてくれました。忙しい日だったので本当にありがたかったです。私が学生の頃もアルバイトさせてもらいましたが、漢方の数の計算がなかなか上手くできずに迷惑をいっぱいかけた事を思い出します・・・。
まだ1年生ですが、数年後には実務実習もあるので、アルバイトでの経験を生かせるようにまた長期の休みにはぜひ来てもらいたいです。
春休みがあと1ヶ月ちょっともあるのかぁ、いいなあ。かなり羨ましいです(笑)
憲法の今後を考える!3/4木村草太講演会
投稿日: カテゴリー:かなえひまわり薬局日記 from:staff
3月4日(日曜日)午前10時から、飯田市上郷別府の南信州・飯田産業センター(旧・飯伊地域地場産業振興センター)で「日本国憲法と立憲主義」と題して、憲法の今後を考える講演会が開催されます。
講師はテレビ朝日『報道ステーション』のコメンテーターなどでもおなじみの木村草太教授(首都大学東京)。参加費は500円。
主催は木村草太講演会飯伊実行委員会で、お問い合わせは飯伊民医連事務局(0265-52-5490)または下伊那労組会議(0265-22-4090)までお願いします。
なお、かなえひまわり薬局では「憲法第9条を変えないでください」の立場で「憲法を生かす全国統一署名」に取り組んでいます。
ご賛同いただける方は、ぜひかなえひまわり薬局店頭でご一筆お願い致します。安倍9条改憲NO!全国市民アクションのページでは署名用紙の印刷やネット署名もできます。
広報誌ひまわりのたね No.42
投稿日: カテゴリー:かなえひまわり薬局日記, ひまわりのたね from:staff
第3回飯田下伊那薬剤師会学術講演会
投稿日: カテゴリー:かなえひまわり薬局日記, 学習会 from:sio
1月24日夜、やまなみ薬局で行われた第3回飯田下伊那薬剤師会学術講演会に出席しました。ひまわり薬局からは4名出席しました。
飯田市立病院 心臓血管内科 部長 片桐有一先生より、『最新の不整脈治療』というテーマで、心房細動についてご講演頂きました。
心房細動の分類、ガイドライン、治療方針、治療薬について、細かく説明してくださいました。
心房細動を有する患者さんには、心原性脳塞栓症が多く発生することがわかっています。心房細動治療において最も大事なことは、脳塞栓症の合併をいかに減らすかということです。その発症リスクの評価方法として、CHADS2スコアがあります。
C:Congestive heart failure(心不全) H:Hypertension(高血圧) A:Age≥75y(75歳以上) D:Diabetes Mellitus(糖尿病) S:Stroke/TIA(脳卒中/一過性脳虚血発作)の頭文字です。
CHADS2スコア(0~6点)が2点以上の中~高リスク症例に対して、抗凝固療法が推奨されています。
CHADS2スコアの年齢のスコアを1点から2点に増やし、新たに3つのリスク因子(冠動脈疾患:心筋梗塞の既往・末梢動脈疾患・大動脈プラーク/年齢65~74歳/女性)を加えたCAHDS2VAScスコアという評価方法もあります。
出血リスクの評価法として、HAS-BLEDスコアが用いられます。
また、手術や内視鏡時における抗血栓療法の休薬のガイドライン、DOACそれぞれの特徴についても説明してくださいました。